催事・発信/新着イベント
シンポジウム 日本の美術館とナビ派-地方美術館から考える研究の可能性【報告】
- 日時:2021年12月13日(月)13:30~17:30
- 開催方法:Zoomミーティング
- 事前予約制:申込みの締切 2021年12月10日(金)21:00
全体の参加者 100名まで・先着順
https://cutt.ly/BRyqX6S(リンク先:Google Forms) - 主催:一橋大学大学院言語社会研究科
- 科研費 若手研究(B)美術制度から見たナビ派の受容と現在(課題番号18K12227)
シンポジウム傍聴記
2021年12月13日、オンラインにて、日本の地方美術館に収蔵されているナビ派の作品に関するシンポジウムが開催された。研究発表として一橋大学大学院教授の小泉 順也教授、広島県立美術館の森 万由子氏、静岡県立美術館の貴家 映子氏、上原美術館の土森 智典氏の4名が登壇した。発表後の全体討議の司会進行を小泉教授が務め、コメンテーターとして国立西洋美術館の袴田 紘代氏が招かれた。また後半にはブレイクアウトセッション(Web会議サービスZoom上でのグループディスカッション)が行われ、これは本シンポジウムの大きな特徴とも言えるものであった。オンライン開催ということもあり、聴衆は遠方からも数多く参加した。研究発表には、学芸員から学部生まで幅広い層が50名近く、ブレイクアウトセッションも20名を超える人々が引き続き集うこととなった。
冒頭のイントロダクションとして、小泉教授より、コロナ禍にあって日本に存在する作品を考えることが西洋美術研究にとって重要性を持つことが改めて強調された。この状況のなか、本シンポジウムはナビ派の作品を収蔵している地方美術館同士の交流の端緒であり、さらに学生が国内で何ができるかを考えるきっかけともなる、またとない機会となった。

はじめに小泉教授が「日本の地方美術館の潜在的可能性−ナビ派の収蔵作品を通した考察」と題し、フランスにおける美術館設立の小史を確認するなかで日本におけるナビ派研究の可能性を論じた。
1793年にルーブル美術館が設立後、その後10〜20年の間に各地でいくつもの地方美術館がフランスのイニシアチブで設立する。地方美術館をめぐる言説として第二帝政期から第三共和政にかけて活動した作家兼美術史家のフィリップ・ド・シュヌヴィエールの言葉をひき、各地に博物館(ミュゼ)が設置される時代が現代に至るまで長く続いていることが確認された。
地方美術館というカテゴリーの有効性については問題が少なからずあるものの、日本でフランス近代美術作品を収集する経緯の継承と意義の再検討を行う時期にあるのではと小泉教授は指摘する。地方美術館の置かれている状況を新たな形で模索する必要があると考える背景には、コロナウイルス感染症の拡大による影響だけでない。展覧会というシステムを用いて美術を再配分してきた美術館連絡協議会が事務局業務を2022年度以降停止すること、また実業家・後藤季次郎氏が蒐集した豊富な西洋美術コレクションを抱えていた山寺 後藤美術館が2021年10月に閉館したことなどが、日本の中からフランス近代美術のコレクションの多様性が部分的に失われた例として挙げられた。
具体的な地方美術館をテーマとした研究手法として、まずはコレクションという視点をもって展覧会を分析することも可能であると提言された。1968年のボナール展(国立西洋美術館、京都国立近代美術館)と2018年のボナール展(オルセー美術館特別企画、国立新美術館)を比較すると両国の美術館にナビ派の作品がどのように受け入れられてきたかがうかがえる。1968年の段階では日本の美術館が出品することはなく個人蔵が多い傾向にあるが、2018年には個人蔵が減って日本の美術館の所蔵が増えている事実に時代の変化を感じることができる。
これ以外にも様々な研究方法が考えうるが、新たなネットワークとデータベースの構築に向けて各地の美術館の所蔵作品やコレクションに複数の人が関われる仕組みを作ることが一歩となる。最終的には大学院生を含めた研究者が国内に所蔵された西洋美術作品を研究する視点を共有することを目標に、美術館側は作品収蔵にまつわる資料を可能な範囲で残し、その経緯や逸話も含めて公開する方法を検討することが必要ではないかと小泉教授からは指摘があった。
次に森万由子氏が「新潟県立近代美術館所蔵モーリス・ドニ作《バッカス祭》研究を回顧して」と題し、2018年に早稲田大学に提出した論文をもとに発表をおこなった。
本発表はドニの完成作・習作がどちらも日本にある稀有な例を用いてなされた研究であり、地方美術館から得られる情報を駆使した成果ということで今回のテーマを具現化した内容だった。対象となる2作品は《ベンガル虎、バッカス祭》(1920年、新潟県立近代美術館所蔵)と油彩画の習作《バッカス祭》(1920年、アーティゾン美術館所蔵)である。日本におけるこの特異な収蔵状況に至った経緯や関連作の基礎情報の提示、また地方美術館の作品がもつ研究の可能性の一例が示された。
新潟県立近代美術館がナビ派の作品を所蔵することになったのは1990年代以降にさかのぼる。前身である新潟県美術博物館が新潟県立近代美術館として新築移転する計画と同時に美術作品収集のための基金が設立、従来の県ゆかりの作家を中心とした日本近現代の作品に加えて西洋近代美術が収集対象となったという。
完成作は1920年にジュネーブの毛皮店「ティーグル・ロワイヤル(Tigre Royal)」店内の階段壁面装飾パネルとして制作されたのが当初の姿であり、取り外し後にオークションに出品され、購入者の家に設置するために画面が分割された。2001年に新潟県立近代美術館が購入したのが、この分割後の大きな部分であったという説明を聞くと、改めてひとつの作品の背後に豊富な情報があるのだと思わされる。
習作段階から完成作への画面の変遷に着目し、構図とモチーフから他の画家やドニ本人の過去作から引用された箇所の意図を探る。そこから森氏は、ナビ派時代とはかけ離れたものと捉えられがちなドニ後期の古典主義的な作品のなかにも象徴主義的な心情が通底していることを導き出す。
森氏は国内の所蔵作品を研究する意義として、海外の研究者もその重要性を認識しつつも海外ではアクセスが難しい代表作は日本での一義的な研究が重要であるという点、習作・準習作についても完成作では前景化していたない要素をときに含むがゆえに主要作の再解釈に通じる可能性がある点を挙げた。日本に実作があることを生かした技法研究や受容研究はもちろん、それ以外のアプローチでも実作が国内にあるということだけで海外の遺族や関係者の協力を得やすく大きなアドバンテージになるというアドバイスは、若い研究者への助言となっただろう。
3人目として貴家映子氏が「東海圏の美術館におけるボナール作品-その多様性と研究の可能性について」と題し、発表者がアクセスできた作品や資料をもとに来歴や購入のきっかけを概観し、その多様性とともにボナール作品の受容史の一端を明らかにした。
貴家氏の所属館である静岡県立美術館ではすでに企画展「STORIES ストーリーズ 作品について学芸員(わたしたち)が知っていること」が2021年に行われており、これは作品の来歴や収蔵後に変化した作品の価値や位置づけを紹介する展覧会であった。本シンポジウムのテーマとも大きく関連性のある内容だったと言えよう。
冒頭で小泉教授が「地方美術館になぜフランス近代美術の作品が所蔵されているか」という問いを投げかけたが、貴家氏の発表も一部その問いに答える形となった。実業家・陶芸家の川喜田半泥子が地元の文化を振興する意味合いで設立した石水会館を源流とする三重県津市の石水博物館にはボナール《港の女たち》(1921年)が所蔵されており、その購入来歴も半泥子の日記から追うことができるという話は興味深い。
東海圏のボナール作品の研究可能性を表すものとして、貴家氏はヤマザキマザック美術館の素描群56点を金沢21世紀美術館学芸員の横山由季子氏と調査を行っている。美術館をまたいだ作品データの共有やデータベース化による受容史研究、作品研究の進展の可能性を感じさせられる。また収蔵館や周辺の館だからこそアクセスできる作品の細部に研究の余地を見出すことも試みられ、貴家氏と上原美術館の土森智典氏がともに確認した作品の造形的・付随的データの共有についても指摘があった。
《ヴェルノンのセーヌ川》(三重県立美術館、1912年)と《ノルマンディー風景》(上原美術館、1925年)では、前者でグレーの下塗りが見えるが後者には下塗りが見られなかったため、画風の変化がなかったと考えられているボナールの作品制作も細部を比較していくと何かしら変遷が分かるのではと思わされるという。また裏面の紙張を見るに同じデータベース上で管理されていた形跡があり、このような写真をオンラインながらも見せていただいたことは非常に貴重な機会だった。
発表からは美術館での研究の重要性を認識させられる一方で、貴家氏は学芸員が専門外の作家や作品の個別的な研究にまでは手が回らない現状を踏まえ、学生や研究者に美術館が持つリソースを積極的に調査・活用してほしいとの言葉を送った。
最後に土森智典氏が「ボナールの絵画における造形的特質-上原コレクションを中心に」と題し、上原美術館所蔵のピエール・ボナール作品について論じた。上原美術館は大正製薬株式会社の名誉会長・上原昭二が蒐集した作品の寄付を受けて開館している。本発表では造形的特質を見るというだけあってオンライン上で精緻な画像をご用意いただき、画面を食い入るように見た参加者も多かったことだろう。
その中でも《海辺の人》(1914年)からは、タッチを拡大すると自然をモチーフにした色彩ではなく絵の具そのものを原色で重ねているということが見て取れた。伝統的な明暗表現(モデリングやシェーディングなどの技法)がないのだ。モチーフに沿わない曲線を重ね、さらにその曲線に沿って曲線を描いていくという作家の筆の動きが想像できるようだった。土森氏はこれを同世代のキュビスムやフォービスムとは違う特徴とし、そのように明暗表現に対する直接的な批評性がないことがモダニズムの批評において位置づけが困難になった所以ではないかと指摘した。
ボナールとは異なり評論家・クレメント・グリーンバーグが高く評価した同時代の作家、マティスの作品を同じ距離の画像で比較することで、ボナールの特徴を改めて認識する試みも行われた。マティスは色が混じり合わないような絵の具の載せ方で明暗表現も理にかなったものだが、対してボナールの手法は単線的な美術史では理解し難いものであると土森氏は結論づけた。
土森氏の発表から、スケッチと油彩画の比較研究の余地が地方美術館だけでも充分にあるという現状、また裏面の情報共有だけでも研究の可能性が広がるだろうということが確認された。実作を見ることが美術史研究において重要であるとの言葉は、発表の後で重みを増したように感じられた。その他にも上原美術館はボナールの宛名不明の書簡なども所蔵しているといい、こうした資料公開のためにも、資料やデータが公開できる制度整備が待たれる。
4名の発表終了後、イベント後半にはブレイクアウトセッションが行われた。ここでは参加者がボナール、ヴュイヤール、ドニ、その他のグループ4つに分けられ、それぞれがオンライン上のルームで活発な議論を行った。各グループには司会者として金沢21世紀美術館の横山由季子氏、国立西洋美術館の袴田紘代氏、三菱一号館美術館の杉山菜穂子氏、小泉順也教授がつき、所属や研究歴の異なる参加者同士の意見交換に寄与した。ともすれば発言量に偏りが出るオンラインイベントだが、このブレイクアウトセッションの利用によって、個々にとって意義深い交流が実現されたと言えるだろう。
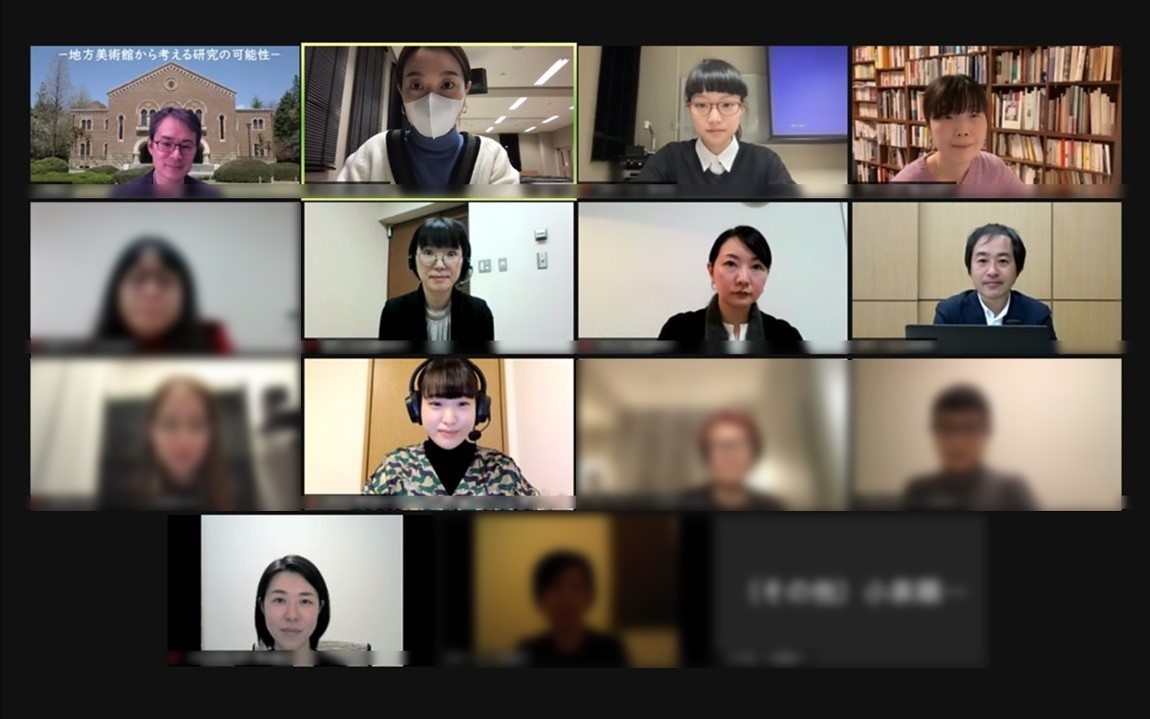
今回のシンポジウムを通して、日本における地方美術館のナビ派作品活用という問題を設定したことで、多くの研究可能性が見えてきた。美術館同士の連携が、諸機関に所属する同分野の研究者や大学院生の研究活動に大きく影響を与えるだろうこと、それがひいては日本の美術館が所蔵する作品の価値向上に与することは間違いない。目標となる環境の実現には制度設計の必要も伴うが、まずは俯瞰的な視座をナビ派研究者が共有することとなった一歩として本イベントが位置づけられるだろう。
文責:山田 小春(言語社会研究科博士後期課程)
ナビ派関連のイベントから振り返る2019年と2021年
一橋大学言語社会研究科の主催のもと、2021年12月13日にZoomで開催された今回のシンポジウムを準備しながら、ちょうど2年前の2019年12月16日に一橋大学で実施したワークショップ「ナビ派の2019年」を思い出していた(イベントの様子はこちらを参照のこと)。一つの会場に発表者と聴衆が集い、終了後の懇親会で遅くまで議論を交わした2019年の記憶は、今では遥か彼方のものになっている。今回ご登壇いただいた広島県立美術館学芸員の森万由子さんは、その参加のために当時わざわざ広島から駆けつけてくださった。Zoom等のアプリケーションを使用したオンラインイベントが当たり前となる世界が、その数ヶ月後に到来するとは誰が予想しただろうか。
とはいえ、新型コロナウイルスの発生から2年近い時間が経つなかで、オンラインイベントの開催は、その特性や利点を積極的に活かす段階に入ったように感じている。オンラインの発表における内容や形式は、残念ながら、対面を前提にしたものと同じにはなり得ない。そのような状況下で、今回のシンポジウムはこれまで温めてきたいくつかのアイディアを試行する機会となった。
たとえば、開催日時を平日の月曜日13:30開始、17:30終了予定とした。他分野では平日の午前中や昼過ぎの開催告知も目にするが、美術関連のシンポジウムではあまり馴染みのない設定である。しかし、大学と美術館の協働を目指すとき、多くの美術館が休館となる月曜日の開催は有力な選択肢となる。最近では週末にイベントが重なることも多いため、平日の活用も視野に入れてよいだろう。
そして、全体を2部構成として、第1部を研究発表、第2部をブレイクアウトセッションに分けたのも、ひとつの工夫であった。ブレイクアウトセッションには、①ピエール・ボナール、②エドゥアール・ヴュイヤール、③モーリス・ドニ、④その他という4つのセッションを設けて、それぞれに司会を立てたが、これは多彩な芸術家が関わるナビ派というテーマであるからこそ実現したと言える。シンポジウムの参加者は約50人を数えるほど盛況であったが、後半のブレイクアウトセッションにも約20人が参加した。各セッションの参加者は、①ボナール(11人)、②ヴュイヤール(3人)、③ドニ(4人)、④その他(3人)となり、こうしたバランスも現在のナビ派研究の状況を反映したものであった。
第1部の参加者には学部生の顔があり、第2部には修士論文を執筆中の大学院生も混じっていた。本来であれば、各種の学会は学生と美術館の学芸員、あるいは他大学の教員との顔合わせの場として機能していたが、例会やシンポジウムがオンラインになって以来、その機会は格段に減っている。このような環境下では、ブレイクアウトセッションが新たなネットワークの創出に繋がる有力な手段となるだろう。ただし、この機能の操作方法、時間を延長する場合の対応、最後にメインセッションに戻ることのリマインドなど、もう少し細かい説明は事前に伝えておくべきであった。
同時並行で進むすべてのセッションの様子は確認できないが、参加者の声を聞いた限りでは、今後に繋がる意義深い時間になったようである。大学院生が美術館の活動やコレクションについて学芸員に尋ねたり、博物館実習(館園実習)の相談をしたりする場面もあったとともに、イベント後に何人かの参加者はそこで知り合った学芸員のもとを訪問したという。シンポジウムを単に視聴するのではなく、文字通り参加する経験になったというのは、企画者としても嬉しい展開であった。
その他にも、Zoomのスポット機能の活用、複数のウェブカメラを使った情報伝達、作品の拡大画像の画面共有など、今できることの反応を実際に確かめる貴重な機会となった。もちろん、実際の画面や音声は通信環境や使用機器に左右されるため、すべての参加者にきちんと届いたのかは分からないが、今後の企画立案の参考になったのは間違いない
今回のシンポジウムの反響のひとつとして、2021年12月21日の静岡新聞夕刊に「『ナビ派』研究の成果披露」と題した記事が掲載された(こちらを参照、最終アクセス 2022年2月13日)。地方美術館という視点を軸に研究を進めていく際は、同地で展開する新聞やテレビ等のメディアとの関係もときに意識する必要がある。さらに印象深い出来事としては、シンポジウムの参加者に釧路市立美術館の学芸員が含まれていた点である。オンラインイベントでなければ接点が生まれなかったかもしれないナビ派研究者の繋がりは、何らかのかたちで今後も発展していくであろう。今回のシンポジウムがその端緒となることを願っている。
末尾ながら、発表者の森万由子さん、貴家映子さん、土森智典さん、コメンテーターの袴田紘代さん、ブレイクアウトセッションの司会者の杉山菜穂子さん、横山由季子さん、企画運営の協力者である博士後期課程の新井晃さん、山田小春さんに心より御礼申し上げる。
小泉 順也(言語社会研究科教授)






