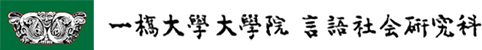修士論文(題目・指導教員名)
2013年度修士修了者論文題目(執筆者から掲載可否の同意を得ているもののみ)
* 1 = 第1部門(言語社会専攻) 2 = 第2部門(日本語教育専攻)
| 題目 | 指導教員 | 備考* |
|---|---|---|
| 海外韓国語教育機関の分析からみた韓国語教育政策 | イ・ヨンスク | 1 |
| 朝鮮半島の文化財保護・返還問題について -日本との歴史から見て- | イ・ヨンスク | 1 |
| 場外馬券場論 | イ・ヨンスク | 1 |
| 北朝鮮における現地指導を通じた政策過程と合意形成 -動態分析を中心に- | イ・ヨンスク | 1 |
| 異文化間移動を経験した子どもたちの教育 -中国から日本へ移動した子どもの母語を中心に- | イ・ヨンスク | 2 |
| Allan Sekula's Critique of Separation | 井上間従文 | 1 |
| 「やさしい日本語」による公的文書の書き換えの諸相 -書き換えの困難語彙の抽出を中心に- | 庵 功雄 | 2 |
| 「やさしい日本語」シラバスを活用したビジネスパーソン向け日本語教育 | 庵 功雄 | 2 |
| 談話における「なんか」の使用実態の考察 | 庵 功雄 | 2 |
| ベトナム語の指示詞がモダリティとして疑問文文末に現れる現象について | 庵 功雄 | 2 |
| 小中学校国語科教科書の説明文における漢語の特性と主要漢語の選定 | 石黒 圭 | 2 |
| 日仏バイリンガル幼児における自然会話の特徴 | 石黒 圭 | 2 |
| 『ヴェニスに死す』の主人公の死が象徴するもの −感情を取り戻す冒険という観点から− | 尾方一郎 | 1 |
| 大相撲の国際化における日本人と外国人の大相撲観 | 尾方一郎 | 1 |
| 石牟礼道子:「故郷」の歴史を遡る | 鵜飼 哲 | 1 |
| 芸術を媒介とした、空間把握をめぐって -ヴォリンゲル、そしてプロティノス- | 鵜飼 哲 | 1 |
| 20世紀絵画にみるハイチ黒人大衆の意識 | 鵜飼 哲 | 1 |
| <歴史>の経験 ー サルトルのアンガジュマン文学 | 鵜飼 哲 | 1 |
| 「復帰」を問い直す 清田政信における音を通して | 鵜飼 哲 | 1 |
| 20世紀初頭の優生思想 −C・W・サリービィの予防的優生学を中心に | 鵜飼 哲 | 1 |
| 戦後思想における田川建三 -赤岩栄、吉本隆明、柄谷行人との交差から | 鵜飼 哲 | 1 |
| 職場をめぐる日本とロシアの比較研究 -異文化理解に- | 糟谷啓介 | 1 |
| カタカナ外来語に関する考察 | 糟谷啓介 | 1 |
| 日本語世界像における時間と空間概念 −間(ま)の概念を中心に | 糟谷啓介 | 1 |
| ステンドグラス作家ガブリエル・ロワールと二十世紀のフランス宗教芸術の動向 | 小泉順也 | 1 |
| 美術館における「私」のものがたりと新たなコミュニティの創出の可能性 | 小泉順也 | 1 |
| ピュヴィ・ド・シャヴァンヌの認知に関する研究 −アミアンの美術館を飾る装飾壁画とその制作過程から− | 小泉順也 | 1 |
| テオドール・シャセオーのオリエンタリズム −アルジェリア旅行以降の作品にみる特色− | 小泉順也 | 1 |
| 『慈善週間または七大元素』 -マックス・エルンストの「前時代志向」と画中画- | 小泉順也 | 1 |
| クリスタル・ケージ -ジョゼフ・コーネルの肖像 | 小泉順也 | 1 |
| タペストリー再考;1900年以降のモリス商会を参照して | 小泉順也 | 1 |
| 吉田秀和のモーツァルト論 〜小林秀雄・河上徹太郎との比較から〜 | 小岩信治 | 1 |
| 要求場面におけるストラテジーの評価と使用に関する -考察 -依頼、不満表明、改善要求を例に- | 五味政信 | 2 |
| 父権制における肉食とベジタリアニズムによる抵抗の可能性 | 武村知子 | 1 |
| 能における<変身>の技法 -知章キリの検討を中心に- | 武村知子 | 1 |
| 中村宏≪血井(1)≫について | 武村知子 | 1 |
| 「ループ」の遊戯:『ひぐらしのなく頃に』の物語更新システム考察 | 武村知子 | 1 |
| 冗長率の効果における媒体の差 -チェルフィッチュ 岡田利規『三月の5日間』を題材に- | 武村知子 | 1 |
| 東野圭吾作品におけるミステリーの犠牲 -作品の味方とトリックの複雑性の喪失について- | 武村知子 | 1 |
| Not Belonging:Jamaica Kincaid's Politics of Difference and Resistance | 中井亜佐子 | 1 |
| 『おそれとおののき』における反復の問題 | 藤野寛 | 1 |
| きめ細やかに考えるための概念とのよりよいつきあい方について −アドルノの『否定弁証法』と音楽論を手がかりに | 藤野寛 | 1 |
| 1950年代中国広西チワン族自治区におけるチワン文普及事業 | 星名宏修 | 1 |
| 地域主義の創出課程におけるアイデンティティの役割 −カムチャツカを事例に | 安田敏朗 | 1 |
| TVCMと和製外来語…TVCM200本の語彙調査に見る和製外来語の特徴… | 山崎誠 | 2 |
| 「Pたり(する)、文型」に関する一考察 | 山崎誠 | 2 |
| 字音接尾辞「的」についての一考察 −前接語基及び中国語対訳表現を通して | 山崎誠 | 2 |