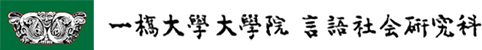修士論文(題目・指導教員名)
2010年度修士修了者論文題目(執筆者から掲載可否の同意を得ているもののみ)
* 1 = 第1部門(言語社会専攻) 2 = 第2部門(日本語教育専攻)
| 題目 | 指導教員 | 備考* |
|---|---|---|
| 伝統競技の担い手の変遷に関する一考察 ー大相撲における「学生出身力士」「外国人力士」に着目してー | 秋谷 治 | 1 |
| 主語位置に生起する再帰形 ー日本語・ロシア語・英語の対照分析ー | 庵 功雄 | 2 |
| 中国語、韓国語、英語話者による「から」「ので」の使用傾向の考察 ー日本語母語話者との比較を通してー | 庵 功雄 | 2 |
| 感謝の場面での謝罪の発話 ー日本語母語話者とタイ語母語話者の意識と使い分けー | 石黒 圭 | 2 |
| 外国人日本語学習者の文章理解における誤理解に関する一孝案 ーウクライナ人大学生を例にー | 石黒 圭 | 2 |
| 日本語と中国語の疑い文 | 井上 優 | 2 |
| 占領期における映画人 ーなぜ第三次東宝労働争議は失敗したのかー | 鵜飼 哲 | 1 |
| ラーエル・レーヴィン・ファルンハーゲン(1771-1833) ー第1期サロンと第2期サロンにおける特徴とベルリン市民社会の変容ー | 尾方一郎 | 1 |
| Plurality within Modern Quebec Identity - Revaluating Rene Levesque as Pioneer | 糟谷啓介 | 1 |
| 留学生と地域社会との交流の視点からみた留学生受け入れ政策 ー東京都国立市における交流事例からー | 糟谷啓介 | 1 |
| 滞日韓国人留学生のコードスイッチング ーコードスイッチングの談話的機能を中心とした考察ー | 糟谷啓介 | 1 |
| 「行為要求表現」における言語行動の日韓対照研究 ードラマから見られる「勧誘表現」の用例を中心にー | 糟谷啓介 | 1 |
| 日英翻訳における異文化要素への対処法について ー新旧版『Botchan』の翻訳スタイルの比較を中心にー | 糟谷啓介 | 1 |
| 風刺画に見られるピノチェト時代 ー軍事政権で出版された風刺漫画の分析と解釈ー | 糟谷啓介 | 1 |
| 日本における「移民」の母語・継承語教育の研究 ーロシア出身のこどもを例にー | 糟谷啓介 | 1 |
| ロシアにおけるろう教育史 | 糟谷啓介 | 1 |
| 「エボニクス決議」:英語からの独立宣言 ー言語戦略家アーニー・A・スミスの役割ー | 糟谷啓介 | 1 |
| 植民地期京城における百貨店とその社会的な影響 ー朝鮮人の消費文化やライフスタイルの変化を中心にー | 糟谷啓介 | 1 |
| V・クレンペラーの言葉に対する二つの視座 ーLTIの分析を中心にー | 糟谷啓介 | 1 |
| 竹内好 ーその態度に関する一考察ー | 糟谷啓介 | 1 |
| 文体と人物像 | 糟谷啓介 | 1 |
| ブルームズベリー・グループの絵画とオメガ工房の室内装飾 | 喜多崎親 | 1 |
| 聖遺物からイコンへ ーボルタンスキー作品にみるキリスト教的形式の考察ー | 喜多崎親 | 1 |
| J.W.ウォーターハウス初期作品に関する考察 ーアルマ=タデマ作品との比較を通じてー | 喜多崎親 | 1 |
| タイ人日本語既習者における電話応対に関する問題点 ービジネス場面を中心にー | 五味政信 | 2 |
| 自然主義の東洋においての変容と発展 | 坂井洋史 | 1 |
| 中国の「春樹チルドレン」 ーアニー・ベイビー、孔亜雷における村上春樹の受容を中心にー | 関谷一郎 | 1 |
| 田村隆一の「戦後詩」の成立 ー詩集『四千の日と夜』における「戦争詩」の可能性についてー | 関谷一郎 | 1 |
| 《フリードリヒ街オフィスビル案》全景透視図木炭画における観察の在り方について | 武村知子 | 1 |
| Differential Intonational Reset in British English | 武村知子 | 1 |
| ミハイル・フォーキンの『新しいバレエ』 | 田邉秀樹 | 1 |
| Shopping and Walking in the Metropolis: Jean Rhys's Impasse in Good Morning, Midnight and Voyage in the Dark | 中井亜佐子 | 1 |
| 国籍を変えるということ ー滞日中国大陸出身者にとっての国籍ー | 坂内徳明 | 2 |
| 『存在と時間』におけるハイデガーの良心概念の射程 | 藤野寛 | 1 |
| 「八相変」の流行とその伝播 ー敦煌写本「雲24号」を中心としてー | 松岡榮志 | 1 |
| 上海における台商家庭について ー教育問題からみる子女の自己認識と中国認識ー | 松永正義 | 1 |
| アンドレ・ジッドの「ソチ」における語り手 ー『法王庁の抜け穴』およびその戯曲翻案を中心にー | 森本淳生 | 1 |
| 大韓民国の文字ナショナリズム「ハングル愛」 ー文字を愛することを考えるー | 安田敏朗 | 1 |