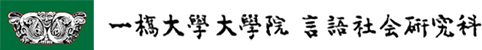《報告》 ヒロシマ・ノワールを思考する/東琢磨氏をむかえて
- 日時:2014年6月24日(火)午後4時〜8時
- 場所:東キャンパス国際研究館5階 共同研究室3
第一部 発表
- 田尻歩(一橋大学大学院言語社会研究科博士課程)
「出来事としての写真と体験されたことのないものについての「記憶」―笹岡啓子の『Remembrance』と『Park City』」 - 片岡佑介(一橋大学大学院言語社会研究科博士課程)
「原爆映画におけるマリア像と母の歌について―熊井啓『地の群れ』を中心に」 - 白木三慶(一橋大学大学院言語社会研究科博士課程)
「ハリウッド・ノワール―The Day of the Locustにおける破滅の社会批評をめぐって」 - 応答:東琢磨
東琢磨氏を迎えて開催された本シンポジウムは、第一部において東氏の著作『ヒロシマ・ノワール』の問題意識と接点を持つ、映像、写真、小説というそれぞれ異なる分野の研究発表が行われた。
最初の発表者である片岡佑介氏は、『長崎の鐘』(大庭秀雄監督)をはじめとする1950年代にGHQの検閲下で制作された映画の原爆被害の語りにおいて、マリア像に象徴される理想化された母親像が多く採用されてきたことを類型的に示し、1970年制作の『地の群れ』(熊井啓監督)での「母の崩壊」をジェンダー論的に読み解いた。戦後、日本の男性保守知識人たちは、アメリカに「父の文化」を見出し、また日本をアメリカに侵された女として見做しつつ、父不在の日本の文化の劣等性を反証するかのように、母の自己犠牲を日本の文化的美徳として位置付けてきた。しかし70年代、もはや赦し受容する母の役割を引き受けない女が登場し、『地の群れ』で50年代に構築された母親像が崩壊することが、映画のラストで失われつつある母の幻想を往生際悪く追い求める登場人物の疾走シーンを、「母の崩壊」にたじろぐ男性知識人の反応として見せているのではないかと論じた。
不在である事の政治性を、写真家・笹岡啓子氏の不定期刊行の小冊子『Remembrance』の分析を通じて議論したのが田尻歩氏であった。それは東日本大震災後の東北の写真を中心に、地表を写し、風景の肌理を感知させる以前のシリーズ作品をも一部収録することで、彼女の写真作品の再アーカイヴ化であると指摘する。しかしそこに、出身地広島の平和記念公園を撮影し、そのモニュメントの不可視性の意味を問う《PARK CITY》シリーズの、滑らかな肌理を持つモノクロの都市の映像は含まれない。ただその不在は、東北の津波と原発事故後の写真によってその滑らかな肌理を否定されつつ、却って以前の「見えない広島」暗示する。そして冊子の断続的な刊行は、出来事を点ではなく、連続な「写真の出来事」として提示し、観者に写真を常に惨事の痕跡と共に見るよう促し、出来事を連続させると述べ、さらにこれらの作品が「遅れた写真」という、出来事の発生から時間を経て撮影するドキュメンタリー形式を採用することで、観者に観照的な態度で出来事を解釈させるよう機能していると指摘する。それは惨事の痕跡を探すという過去への取り組みであると同時に、個人的な記憶の枠を越え、未来の来るべき想起の瞬間に向けた待機であると締めくくり、社会に関与する芸術の一つの在り方を我々に提示した。
最後の白木三慶氏の発表は、1930年代のノワール小説の傑作、ナサニェル・ウェストの『いなごの日』にファム・ファタールとして登場する女優志望のフェイ・グリーナ―を、ハリウッドという世界のメタファーとして考察し、小説における「ノワール」の意味を追究するものであった。作者ウエストと重ね合わされる主人公トッドは、自らのフェイへの欲望を通じてハリウッドへの考察を深めていると指摘する。フェイの描写は身体を物質として扱うものであり、またその魅力はフェイに群がる男たちがそれぞれに他者の欲望を模倣することで生みだされていると分析する。このような分析を通してこの小説は、ハリウッドの魅力の裏側をも暴き出し、人間性を失ったハリウッドの、そのスクリーンの裏側で挫折し破滅していった人々を覆う闇こそが「ノワール」であり、『いなごの日』あるいはハリウッド・ノワールを通じて歴史に記録されない人々に思いを巡らす事が出来ることを示唆した。
第二部 東琢磨『ヒロシマ・ノワール』をめぐって
- 書評 有坂美紀、吉田裕、井上間従文
- 応答とトーク 東琢磨

第二部では、『ヒロシマ・ノワール』を三人の評者がそれぞれの視点で読解し、最後に著者である東氏のコメントが寄せられた。
有坂美紀氏は、まず東氏が今日我々の権利が義務を果たすという条件の下で認められていることを問題化した議論を受け、広島が反戦・反核を訴え、承認を求めてきた運動がいつしかヒロシマのアイデンティティとして本質化され、それがネオリベラルな状況のもと、価値ある商品として見做されるようになったと論じる。そしてシベリア抑留中を「自由」と呼ぶ石原吉郎への東氏の言及について、その「自由」は「近代的国家」において「一般に」人類と想定されるものに特権的な自由とは異なり、まさにアガンベンの「剥き出しの生」としての非人間的とも言える自由でしかないが、しかしそれは承認を求めなくても基本的人権が担保された状況を失った今日のネオリベラルな社会状況では、広島のみならず我々自身商品となることから逃れられない状況にあることを示唆しているとする。このような希望のない状況からの脱却のために、東氏が非人間的な幽霊の存在を認め思考するフレームを持つことに可能性を見出していることに言及し、神話や伝承的世界観によって科学的なものとの二項対立を無化し、今一度権利や人間という概念に逆側から光を与え得ることを本書は示唆していると述べた。
井上間従文氏は、東氏の前著『ヒロシマ独立論』のエスノグラフィックなアプローチが、『ヒロシマ・ノワール』では「ノワール」を介して美的感性的なものに関わろうとするように思えると評し、フレッド・モートン、アミリ・バラカ、新城郁夫らが、闇による盲目の中で、あるいは沖縄という表象としては見えない場所で「聞く」ことに留意したこととの連続可能性を示唆した。また東氏が幽霊論で触れる「フィギュア」を、リオタールやナンシーらの論じるカテゴリー化や形象化を逃れるthe figuralの問題へと独自に敷衍しつつ、本文に引用された様々な事柄の中に抵抗する輪郭や境界線の存在を見出し、そこで述べられている、「感情」に寄り添いながらローカルな地点で抵抗すること、それがfigurativeなものから解放される道筋として本書に埋め込まれているフィギュアであると評した。
広島を「ノワール」と表すこと、また田尻氏が言及した広島の平和公園が昼間の白と夜の闇によって「見えない」とされることに対し、吉田裕氏は以前観たみずみずしい色彩の映像記録を想起したと冒頭で語った。「ノワール」の意味を様々に探り、かつてのアパルトヘイト賛成派を探すことは、実体のない幽霊を追うようなものだという記述をZoë Wicombから引用し、ここでの幽霊は差別的体制に共犯的だった人間が過去を忘却し、隠蔽する事、あるいは忘却したことを忘却することをfigureとして表しているのではないかと問い、そこから冒頭のカラー映画について思考することが出来るのではないかと述べた。
以上の発表・書評を受け、東氏は最後に執筆の経緯を明かしつつ、原発事故後に目立った、「地方対中央」という二項対立的な見方では見えない地方のエリート層を、植民地エリートについて思考する枠組みで捉えなければならない事、またかつてあった土地を収奪して人々を移動させるという暴力ではなく、汚染地域の人々を実際にディスプレイスさせながらも、土地への愛着を美化したうえで、ある他の人々を移動させないという暴力が働いている問題に触れ、解決が阻まれることへの怒りやいらだちを吐露した。「移動/定住」という分断と位階化の二項対立を生む表象の仕組みを疑いながら、同時に「ローカル」や「民衆」を擁護する方策について東氏は語った。そして視覚優位の現在において、今後は音の問題により一層取り組みながら、何らかのものを生み出していかねばならないと語った。
報告者:竹田 訓子(言語社会研究科博士課程)